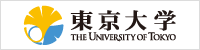【報告】CPAGラップアップシンポジウム「“新しい普遍性”をめぐる東アジア三方対話」
2014年11月14日(金)、東京大学駒場キャンパス18号館4階コラボレーションルーム2において、GPAGラップアップ・シンポジウム「新しい普遍性をめぐる東アジア三方対話」が開催された。はじめにGPAG代表の中島隆博氏(東京大学)が、挨拶と趣旨説明を行ったあと、三つのセッションが展開された。以下、喬志航氏による報告をお送りする。
第一部は、許紀霖氏(華東師範大学)、邱立波氏(華東師範大学)、王前氏(東京大学)の三名による報告であった。
許紀霖氏は「共有可能な普遍性―「新天下主義」とは何か」と題する発表を行った。許氏は、東アジア各国におけるナショナリズム意識の高まりに対し、それを低減させる思考意識として「新天下主義」を打ち出し、さらに、いかにこの「新天下主義」によって東アジア、ひいては全世界に新しい秩序を再構築するかを論じた。許氏の解釈においては、「新天下主義」は、古代の伝統に由来しつつ、そこに近代的な解釈を加えた、枢軸文明の叡智であり、天下主義2.0という新ヴァージョンである。それは、旧来の「天下主義」と比べて、二つの新しい点がある。一つ目は脱中心化、脱等級化である。つまり、「新天下主義」は、「承認の政治」を原則として各国民国家が主権平等と相互尊重を守ることに基づくが故に、伝統の天下主義と国民国家の双方に対する超克である。二つ目は新しい普遍性としての天下を作り出そうということである。それはすなわち、様々な文明や文化の「コンセンサスの重なり合い」を基礎にする、異なる国家と民族によって共有される近代文明である。これを踏まえ、許氏は「新天下主義」のもとで東アジア運命共同体がいかにして可能かを検討した。冷戦後の東アジアは、普遍性の不在状態にあり、その関係は無秩序で変化しやすく、極めて不安定である。東アジアにおける普遍性は、歴史的遺産の基礎の上に立って、新たに構築され創造される必要がある。許氏は、新天下主義はまさに、歴史を継承しつつ超克する新しい普遍性のプラン、つまり、帝国の伝統を発展させたもので、単一で普遍的な文化的特徴を持ちながら、同時に帝国の中心化と等級化を取り去り、内部における宗教・体制・文化の多元性を保持しているものであり、それは脱帝国化された帝国の再生であり、民族と国家を超えた平等の共同体である、と力説した。

邱立波氏は「文化、アイデンティティ、それとも政治?――東アジアの普遍性をめぐる課題としての三つの変数」と題する発表を行った。邱氏は、文化やアイデンティティをもって東アジアないし世界を統合することで引き起こされる問題は、解決できる問題を上回るだろうと指摘し、政治的視点を取り戻すべきだと述べた。邱氏のみるところ、中国では長らく一種の安定した構造が保たれている。この構造は、すなわち中原の民族は一貫して経済的機能を担い、その一方で周辺の強力な民族は基本的政治機構を提供する、ということである。換言すれば、中国では長きにわたり政治が欠落し、経済と文化だけが発達してきた。19世紀半ば以来、アジアの政治的安定の主要な基盤は、ヨーロッパ列強が東アジアにおいて築いた、近代的国際条約システムを主要構造部とする政治勢力的均衡であったため、東アジアは、単なる政治的―地理的概念にとどまったままであった。その後、近代日本のアジア主義は、東アジア民族による自主政治の比較的早い試みであるが、依然として強烈な独断性と閉鎖性を帯びている。1949年以降、中国の国家意識においては、二種類の普遍主義的、あるいは少なくとも汎地域主義的な政治的言説が存在していた。一つはプロレタリアートによる世界革命の物語であり、もう一つは経済を媒介とする対外開放に関するものである。しかしながら、邱氏によれば、上記の二つとも反省を経ることなく、中国の特殊性を通して表現されたのであり、前者は中ソによる新覇権の追求の物語にすぎず、後者はさらに周辺各国の民間社会による自発的抗争という挑戦を受けているが、問題の政治的実質が隠蔽されたため、こうした抗争が汎人種化あるいは汎文化化されることになった、という。邱氏によれば、中国が現在、周辺および世界の他の地域において直面している政治問題は、中国の政治秩序あるいは国家哲学に対する現在の世界秩序からの、ある種の全体性を伴う反応であり、中国内部もまさにこの中国政治に対する最も厳しい挑戦に直面している。現在の中国外部の政治的危機は、すなわち内部の政治的危機の反映であり副産物だといえる。ゆえに、政治問題を回避しようとして文化―アイデンティティ的思考をとることは、政治性を緩和しないどころか、かえって政治性を激化し、さらには中国「例外」論に理論的基礎を用意し、よって権力は分立し、一方と他方は牽制しあう必要があるかなどの問題を回避することによって、大規模な民族主義がもたらした結果に直面せざるを得ないことになる、と邱氏は発表を締めくくった。

王前氏は「丸山真男とカール・シュミット――新しい政治哲学のために」と題する発表を行った。王氏は、丸山政治哲学の目的は自由民主を日本に深く定着させるために理論的基礎を作り出すことにあり、一方シュミットは近代議会政治および自由民主主義に批判の矛先を向けたにもかかわらず、丸山は終始シュミットを重要な対話者としながら、その思索を深めていた、と指摘した。丸山は政治思想におけるシュミットの貢献を高く評価しただけでなく、自由民主政体に対するシュミットの多くの批判にも賛辞を呈したが、基本的な価値においてシュミットとは正反対である。すなわち、丸山は基本的に英米の伝統的な自由民主主義政体を支持し、彼の考えた「近代的思惟」において自由民主の政治体制は主要な部分を構成する。王氏は、丸山が互いの政治的コンテクストの相違をはっきり認識して、シュミットの批判したのがただワイマール共和国の未熟な議会制にすぎないと考えたという点を。両者における差異の原因のひとつとして捉えた。むろん、丸山はシュミットが指摘した自由民主政体に含まれているさまざまな欠陥を無視したわけではない。王氏によれば、丸山はシュミットとの対話を通して、議会制民主主義が面した問題の解決法を探り、一般民衆の政治への参画を強調して、民間の自主的組織、たとえば労働組合を通して民意の反映ルートを構築することにより、民主主義の硬直化を防ごうとした。丸山は完全な自由民主主義理論を作り出さなかったものの、彼の触れた政治的問題が今日でも未解決のままであり、現存の自由民主政体における問題およびこの政体に対して、彼の示した理論的説明は、21世紀においても依然として啓発的だと、王氏は結論付けた。

第二部では、劉擎氏(華東師範大学)、崇明氏(華東師範大学)、金杭氏(延世大学)が報告を行った。
劉擎氏は、「共に構築する普遍性の探求――天下思想から新世界思想へ」と題する発表を行った。劉氏の解釈によれば、天下認識は、中華文明と対峙するという意味での真の「外部」を想定できない。しかも新しい普遍性は、既存のある文明の内部に存在する思想ないし伝統を見だして、それを全世界に広げるものではない。それゆえに、旧来の天下観は自身が凋落する運命に直面し、さらに教訓を汲み、自分自身を変え新しい世界秩序に順応しなければならない、という。この「天下主義」に対して、劉氏は、「新世界主義」を主張した。いわゆる「新世界主義」は「共に構築する世界」である。このような「共に構築する世界」は、普遍性を一種の文化構築、すなわち、種々のローカルな場で想像された普遍性が互いに学び合い、コミュニケートするプロセスのなかで形成され、同時にローカルの相対性に制約されているものだと見なしている。そのため、「新世界主義」は本質主義の視点で特殊性と普遍性を理解することを拒否し、「自己問題化」、「他者に学ぶ」および「自己転換」を強調する。劉氏によれば、各々の民族文化はすべてこの、共に構築する世界の資源である。しかも、文化共同体が「他者」と遭遇(encounter)するたびに、自分自身への再認識を導き、さらに文化の自己転換と創造力を激発することができる。そして、このような自己転換の可能性は、個々の文化のコミュニケーションを、いわゆる「コンセンサスの重なり合い」を超えて、一種の通文化的普遍主義を作り出すはずだという。劉氏はまた、もし中国文化がこのように学び合い、コミュニケートするプロセスに参加するならば、新しい世界への想像に貢献できるだろう、との見解を付け加えた。

崇明氏は、「国民国家、天下と普遍主義」を題として発表を行った。崇氏は、中国における天下主義の復活にあたって、国民国家への問い直しを迫るもので、新しい普遍性を考える場合に民族国家が依然として有意義であることの証明を試みた。崇氏によれば、天下概念は帝国秩序のある種の変形にすぎず、国民国家の出現こそ、不平等や支配関係の上に成り立っていた帝国秩序を覆した。そして、天下とは意志的なものであって、明確な政治共同体の構造ではない。天下主義は政治体に何かしらの統治術を提供できるかもしれないが、共同体に転換させる政治的正当性を付与するものとは成り得なく、その遺産は政治的共同体を作る際の大きな負担さえ伴う、という。さらに崇氏は、天下主義は、非儒教圏や漢民族以外のエスニックグループを、一つの政治共同体のなかに整合的に組み入れたことが一度もなく、単なる緩い文化的・政治的つながりを保つにとどまり、正しく向心力のある政治共同体を作り上げる力がないため、天下主義は今日中国の民族問題にうまく対応できるとは考えにくい、と指摘した。これに対して、国民国家は往々にして自由民主政体をもってその仕組みを固め、異なった民族の人々や異なった宗教の信者たちが、民族や宗教を超えて互いを市民として扱い、政治共同体の事務に参加することを勧めることにより、国民間の政治的関係は民族や文化間の関係に比べ、優位に立てることとなる。したがって、国民は自由な政治生活を通じて、人間の普遍性――自由と平等の主体としての人間――を理解することができる。国民国家は普遍主義を排斥するわけではない。むしろ普遍主義は国民国家の自己同一性の重要な要素となっており、しかも、普遍主義が政治共同体をキャリアとしなければならない。崇氏の考えでは、現代中国の領土、民族問題は、国民国家という政治的形式自体に由来する部分もあるが、それより政体の形式、つまり国民国家を作り上げ、その政策を実際に遂行する際に不当な方法をとったことに由来するものが多い。崇氏は、天下主義は現代政治の正当性の根拠とは成り得ないが、修正した上で、いかに共同の政治生活を通じて国民の共同体への自発的な共感を作るのか、という問題に取り組む上では寄与可能だという見解を示した。要するに、いわゆるポスト民族構造は、国民国家が解体に向かいつつある状態ではなく、自らを開き調整することで普遍主義を確実に実現する過程となるべきだと、崇氏は指摘した。

金杭氏は、「20世紀から退却する道:脱普遍と政治的なものの再構成」を題として発表を行った。金氏は、20世紀の普遍主義に対する批判の準拠として「敵」という概念を取り出したシュミットと、レオ・シュトラウスのシュミット批判を取り上げ、20世紀が行き着いた近代文明の極端な臨界点を突破し、新たな生の形式を模索するという意味では、「政治的なもの」はいかに思念されうるべきか、言い換えれば、我々はいかに我々の時代に必要な政治哲学を奪還するかという問題について、議論を展開した。金氏によれば、シュミットは「友/敵」の対立を国家主権と法の存立を保障するものとし、自由主義・多元主義的な秩序が「敵」を普遍的人間性という名のもとに人類の外へ追いやったことを退ける。しかしそうすると、政治的な抗争における双方の言い分を同等に認め、何が正しいのかという判断に関心を寄せないことになる以上、道徳的判断が政治的なものから追い払われることとなる。一方、シュトラウスは、「敵」が個人そのもののなかに潜在性として潜んでいると考え、人間が己のなかで常として「敵」と向き合うことを近代的な政治企画の要諦として位置づけた。したがって、人間の危険性は正しい生と秩序を作り出す内在的な道徳的基礎となった。両者ともに、近代的な政治企画が危機に直面したのは、「敵」がグローバルな秩序と近代的合理主義のなかに姿を消したからだ、という。しかし金氏は、敵は消え失せるのではなく、グローバルな秩序と近代合理主義によって変容を蒙ることとなったと指摘した。金氏の解釈において、こうした変容は、国際法における「海賊」認識、つまり、海賊行為をしたものはいずれの国にも属さず、普遍的な人類と進歩の理念に敵対する「全人類の敵」であるという思考方法に基づいて、「敵」を殲滅されるべきもの、非正常なもの、不気味なものとして虐げる、ということである。従って、いかにしてこのような思考方法から抜け出る、と同時にシュミットやシュトラウスのように、「敵」の現前を追い求め、ひたすら実存的かつ現実的な敵対を促す「決断」の政治へと舞い戻るのとは別の帰結へと辿り着けるのか。これが金氏の問いである。金氏によれば、現在要請されている思考と実践は、「敵」を普遍と対決の場からずらして、「戦争の記憶」より「戦場の記憶」をもって歴史経験を共有することによって、共存を図ろうと試みることである。戦場で「敵」は普遍的な理念や国家主体などへと還元し帰属させておらず、お互いの暴力にびくびくする、ひ弱な存在でしかない。20世紀から脱却する道の一つの可能性は、このように「戦場」において「敵を愛す」ことにあるのではないだろうか、というのが金氏の主張であった。

第三部の講演者は、梶谷真司氏(東京大学)、李永晶氏(華東師範大学)、石井剛氏(東京大学)の三名である。
梶谷真司氏は、「危機意識と伝統への回帰――日本における医療批判と伝統医学の形成」と題する発表を行った。梶谷氏によれば、人間が何らかの社会的危機に直面し、特にそれが外来の要因によるとされる場合、しばしば自らの伝統へ回帰することで解決を図る。そして、いわゆる「伝統」は単なる過去やその継続ではなく、当の文化が本来の拠り所とすべき規範だということである。しかも、このような規範は、何らかの連続性を持ちながらも、時代ごとの状況に応じて異なった、新しい形を取ることが多い。梶谷氏は、日本における医療批判、具体的に言えば、江戸時代の古方派による中国医学批判、明治大正時代に起きた漢方復興における西洋医学批判、そして60年代以降現代の医療批判における東洋医学の復権、という三つの例をとりあげ、いわゆる「伝統」がどのようにして形成されるのかを考察した上で、そこにはある程度の一貫性、整合性がありながらも、時代ごとにかなり変化している点が多くある、と指摘した。こうした議論を踏まえて、梶谷氏は、そもそも「伝統」とは何であるか、あらかじめ決まっているわけではないとすれば、近代社会の問題を解決するために伝統に回帰することは有効であるか、仮に伝統のなかに何か手がかりがあるとしても、それは果たして何なのか、いかに生かされるべきか、と問うた。

李永晶氏は、「「天下」から「世界」へ――東アジア儒学秩序原理の過去と未来」と題する発表を行った。李氏は、「天下」という区域―世界秩序原理の、歴史上の四つの時期における具体的な出現を論ずることによって、この概念が、普遍的文明秩序が形成される今日において有意義な思想と歴史的資源を提供しうるかを問題とした。この四つの時期とは、一、伝統的中華世界秩序が相対的に平和と繁栄を維持している時期――「天下」概念が形成され、空間秩序、相互承認の原理、文明を伝播する手段、それに政治共同体の政治的戦略を加えた四つの面を内包している。二、中華帝国の衰退期。「中華」としての中国が弱体化するのに伴い、もともと中華世界の周辺に位置してきた日本は、さまざまな形で語られたアジア主義を通して、日本を中心とする新しい東アジア世界秩序を確立しようと試みた。三、1949年以降の共産主義時期。中国が提出した「三つの世界」論には、天下主義と共産主義の新しい結合が見られる。というのは、第三世界のプロレタリア革命を通して、中国が再び世界の中心に舞い戻り、こうした周辺―中心の転換という点からすれば、この世界認識論は形式上、天下概念の認識構造を継承しているからである。四、1980年代以降のポスト革命時代。急速な経済成長を伴い、世界の文明化の過程において、中国の役割は日に日に突出してきている。「天下」論も再び勃興しつつある。こうしたなか、問題はいかに「天下」論の再現を理解すべきかという点にある。李氏によれば、第二次世界大戦以降に形成されたアメリカを中心とする自由世界システムは、近代中国が幾度も経験した屈辱的な強権的政治システムとは異なるものである。しかも、このような普遍的世界秩序は、グローバルな共通認識と、それにふさわしい制度上の保障を獲得した。それゆえに、「天下」論は、こうした真の世界主義的な視野を取り入れてはじめて、その思想的可能性を発揮することができる、と李氏は強調した。

石井剛氏は、「「文」――「和して同ぜず」のなかで「他者」に直面する芸術」を題として発表を行った。暴力の連鎖を断ち切るため、「和」が打ち立てられ、国々や国際機構の共同認識となったが、「君子、和して同ぜず」が示したように、「和」になる基礎が「同ぜず」を強調することにあると考えるがゆえに、石井氏は孔子および和辻哲郎を例にとって、「和」を追求する際、一つ一つの個体に他者との「不同」をいかに保持させるのかを論じた。石井氏によれば、孔子は「文」を暴力に抵抗する唯一の武器とする。「文」は文章と文化との二つの意味を持つ。それは無限で時空を超える読みの経験であるが、特定グループに専有されるものではない。「文」のなかで出会った人々は、知を求める実践を通じて、ある共通体を作り上げる。このように「文」のもとに「共通」を求めることは、我々に「同ぜず」を保持させることを可能にしながら、危機に瀕する際、共に前進することを可能にする。一方、和辻哲郎はしばしば「共同態」概念を用いる。石井氏は、和辻の「共同態」は「文」の「共通体」とは異なっている、と指摘した。というのは、「人」は最初から社会的存在であり、間主観的な自己であると主張する和辻は、自己意識の社会的性格を形成するコネクションを「間柄」といい、個体の独立を維持させるとともに、間主観性を再構築しようとしたが、その「間柄」には「他者」が不在のため、結局「間柄」は「我々」になり、つまり、「同」に回収されたからである。とすれば、いかに他者に向かうべきか?石井氏は、レヴィナスの他者論が述べた「愛」の超越性をもって「他者」に向かう提案、そして言語の超越が「愛」に結びついているという指摘に注目した上で、他者へ向かう際に「文」の可能性がどうなるのかについて考えなければならない、と主張した。

各セッション後のディスカッションでは、フロアも交えて濃密な議論が展開された。時代につれて変化してきた「天下」概念の複雑性や、「新天下主義」と近代性との関係などが話題となった。最後にシンポジウムの総括として、ラウンドテーブルが行われた。まず白永瑞氏(延世大学)と中島隆博氏から、それぞれ発題が行われた。白永瑞氏は、「新天下主義」は西洋の思想的資源に関心を寄せているが、東アジアにおける、中国以外の国々の思想的資源をさほど重視しておらず、しかも、「天下」概念は華夷秩序のように段階的な秩序構造を伴うため、西洋中心主義を打破したが、代わりに容易に中国中心論を復活する恐れがあると批判した。その代案として、「道」概念がより注目すべきだという指摘がされた。中島隆博氏はまず、三国の大学の研究者が集まって「新しい普遍性」について討論すること自体は有意義だと述べた。というのは、この普遍性は事前に設定済みのものではなく、みんなの参与が必要なプロセスである、と証明したからである。続いて中島隆博氏は、「理一分殊」を提示し、「理」と「天」を対照した。さらに、必要なのは、強烈な概念より、むしろ弱い概念だと指摘し、「地人」概念を提起して、超越的な立場からではなく、「地人」とともに地上の普遍性を作ろうと主張した。その後フロアからは、多岐にわたる質問、話題、視点が提示され、「新しい普遍」をめぐる、豊かな展開の可能性が示されたシンポジウムであった。


報告:喬志航